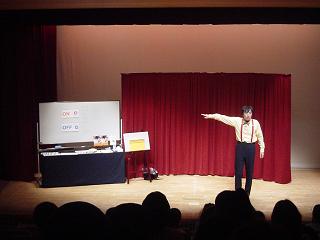本当はブログなど書いている時間はない、はず、なのだが・・・極度の忙しさとストレスで寝られない日々が続いている。迫りくる原稿の締め切り、舞台の仕事、公演の準備、授業の準備、学生の指導、試験の採点、事務仕事、論文のスピーチ原稿、etc, etc・・・最近は朝10kmのランニングもサボっている(涙) おいおい、このままじゃメタボマイムになるぞ~!! メタ、メタ、meta?…….メタ・認知(metacognition)という言葉がある。自分の情動について客観的視できる能力のことだそうだが、今の自分は完全にこの怒涛のvicious cylce (悪循環)の中に完全に足を取られて抜け出せずにあがいている状態だ。ん~思い切って二時間くらいヨガができれば・・・なんて考えつつ、体がついてこない
以前このブログで自分の携帯アドレスのことに触れた事がある。and this too shall pass…
2001年にBS放送「この人この芸」という番組に出演したときに「好きな言葉は?」ととっさにアナウンサーに聞かれて答えたものだが・・・「そして、これも過ぎ去るもの」直訳すればこのようになるが、実はこれには深い意味があるのだ。
その昔、ソロモン王が側近の賢者に「苦しみのどん底にいる人間が聞いたら歓喜に踊り、幸福の絶頂にいる人間がきいたら愕然とする」そんな知恵の塊りをさがしだせと命令したそうな。その賢者苦労して全国行脚し、ある日露天商の前を通りかかった。さてさてその露天商の老人がならべる骨董品を見渡していると、その老人が「何かお探しか?」と聞いてきた。賢者は事の成り行きを話すと、その老人は「ならこれはどうかの?」といって、おもむろに商品の中から指輪をとりあげ、そこになにやら言葉を掘り出したそうな。賢者はその指輪をソロモン王に持ち帰ると、王はまさしくこれはその知恵に間違いないとご満悦だったという。
苦しみも、幸せもいつまでも永遠に続くものではない、そしてこの瞬間も常に過ぎ行くものである・・・こんな意味だろうか。つまり所業無常。闇が深ければ夜明けはそれだけ近いという。ん~もっと暗くなりそうだ(苦笑)これもまた過ぎ行くもの・・・深いな~ デモ過ぎたら楽しい思い出なんだろうな~(笑)こんな繰り返しが人生かも・・・そして何度これを繰り返してきた事か。 今できる事、それは今を味わう事。そして吾唯足知(吾唯足る事のみを知る) 今が一番!!楽しまなくっちゃ。だって今しかないものね。この文章多少分裂ぎみです。失礼(写真は今の自分の癒しグッズ!? 息子の寝顔を下から撮ってみました爆)
-
ブログ最新エントリー
ブログカテゴリ
- イベント (7)
- つれづれなるままに (671)
- ひとりごと (259)
- ワークショップ (9)
- 中学校公演に寄せられた感想 (4)
- 公演 (28)
- 告知 (55)
- 学位 (4)
- 小学校公演に寄せられた感想 (3)
- 高校公演に寄せられた感想 (3)
以前の記事
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (4)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (3)
- 2024年9月 (1)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (8)
- 2023年10月 (2)
- 2023年7月 (10)
- 2023年6月 (3)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (4)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (1)
- 2021年11月 (3)
- 2021年7月 (3)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (4)
- 2020年1月 (2)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (5)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (3)
- 2018年12月 (7)
- 2018年11月 (9)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (7)
- 2018年8月 (11)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (5)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (3)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (10)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (5)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (8)
- 2013年6月 (6)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (6)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (5)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (10)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (7)
- 2012年7月 (9)
- 2012年6月 (10)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (8)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (10)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (7)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (6)
- 2011年7月 (11)
- 2011年6月 (10)
- 2011年5月 (6)
- 2011年4月 (8)
- 2011年3月 (14)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (9)
- 2010年12月 (11)
- 2010年11月 (13)
- 2010年10月 (9)
- 2010年9月 (10)
- 2010年8月 (6)
- 2010年7月 (9)
- 2010年6月 (7)
- 2010年5月 (8)
- 2010年4月 (13)
- 2010年3月 (14)
- 2010年2月 (10)
- 2010年1月 (5)
- 2009年12月 (12)
- 2009年11月 (10)
- 2009年10月 (14)
- 2009年9月 (10)
- 2009年8月 (10)
- 2009年7月 (11)
- 2009年6月 (9)
- 2009年5月 (12)
- 2009年4月 (6)
- 2009年3月 (10)
- 2009年2月 (16)
- 2009年1月 (11)
- 2008年12月 (10)
- 2008年11月 (8)
- 2008年10月 (12)
- 2008年9月 (4)
- 2008年8月 (13)
- 2008年7月 (18)
- 2008年6月 (9)
- 2008年5月 (11)
- 2008年4月 (7)
- 2008年3月 (13)
- 2008年2月 (6)
- 2008年1月 (12)
- 2007年12月 (9)
- 2007年11月 (5)
- 2007年10月 (5)
- 2007年9月 (8)
- 2007年8月 (2)
- 2007年7月 (14)
- 2007年6月 (6)
- 2007年5月 (5)
- 2007年4月 (13)
- 2007年3月 (1)
- 2007年1月 (1)
- 2006年12月 (2)
- 2006年9月 (1)
- 2006年7月 (3)
- 2006年5月 (1)
- 2006年4月 (1)
- 2006年3月 (1)
- 2005年12月 (1)