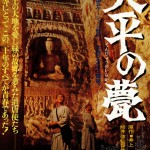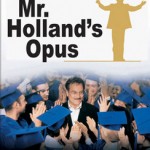今回は、「天平の甍」1980年版。1957年の井上靖の歴史小説を映画化したものです。僕はこの映画に非常に影響を受け、その後の生き方を変えられたといっても過言ではありません。この映画を見たとき、僕は仏教の「戒」というものに関して初めて真剣に考え、そして勉強しました。その約十年後に自らインドのブッダガヤ(釈尊がその下で悟りを開いたとされる菩提樹がある)を訪れ、菩提樹下で受戒をするという経験に繋がっていきます。
もともとインド(天竺)で発生した仏教には釈迦が説いた教え(経)と共に、釈迦が弟子たちに課した戒律(戒)というのがありました。その戒を釈迦より授かり、自分が仏教徒として生きてゆくという宣言をした時点から人は釈迦の弟子として仏教徒となります。つまり、クリスチャンが洗礼を受け、洗礼名を頂いて正式なキリスト教徒として生きてゆくのと同じことです。つまり、戒名とはクリスチャンネームならぬブッディストネームなのです。ゆえに、日本の社会の現状のように死後、高額なお金を払って遺族がお坊さんから名前をもらうというものではなかった筈。このことを深く考えさせられたのがこの映画でした。
当時の日本(天平の時代)には日本には釈迦の教え(経)は伝わってはいたが、その経に従い生きてゆく上での約束事(戒)を授けられる専門の僧の存在が皆無でした。勿論、従って戒律を授かる戒壇という設備もない。そこで大陸より、授戒できる高僧を招聘せよという聖武天皇からの命を受け、第九次遣唐使で大陸(唐)に渡った若い留学僧たちの話です。
普照(中村嘉葎雄)と栄叡(大門正明)は命がけで大陸に辿りついた後、様々な寺を訪れ、日本に戒律を伝えるべく同行してくれる僧を訪ね歩くが、当時国禁を破り自らの命を懸けて海を渡ろうとする僧にはなかなか会う事ができなかった。そんなある日、742年、二人は揚州の大明寺の住職であった鑒眞(鑑真)のもとを尋ねる。多くの弟子に鑑真は渡日の希望を尋ねるが、危険を冒してまで渡日を希望する者は誰一人としていなかった。すると鑑真が自ら同行しようと名乗りでる。真の教えを命を懸けても布教する仏教の本来の布教の精神を遂行する為だと、、、それに心打たれた21人の僧も同行を希望する。だが、5回、出国を試みるが5回とも密告、難破などにより出国に失敗する。
僕は、もともと遣唐使、遣隋使に憧れていたのですが、それに加え、この経験の少し前に出会った新渡戸稲造の「太平洋の橋になりたい」という言葉、つまり異文化にかける橋になるという夢を持っていました。そこでこの遣唐使の話に興味を持ち、映画を見たわけですが、インパクトはそれ以上のものがありました。こののち僕は鑑真和尚の由来の寺である奈良の唐招提寺を訪れ、鑑真和上に心より御礼を申し上げました。現在では入手が困難なようですが、この映画はお勧めです。真の仏教徒の生き方が見事に表されています。