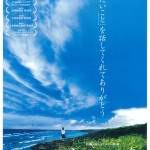「グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち」
台本は当時ハーバード大学在学中であった、マット・デイモンが、シナリオ製作の授業で書き起こした戯曲を親友のベン・アフレックの協力で映画化に向けた脚本を共同で執筆したというもの。若さ故の斬新な発想、エネルギーが溢れる作品です。
物語の舞台はMIT、世界屈指の天才達が集う、マサチューセッツ工科大学から始まる。数学科教授のジェラルド・ランボーは、学部の学生たちに代数的グラフ理論の超難問を出題しそれを廊下の壁に提示し、学生に解けるか挑戦する。天才学生たちがみな悪戦苦闘する中、ある日正解を出す者が現れた。その人物は実は大学の学生ではなく、なんと!アルバイト清掃員の青年ウィル・ハンティングであった。このウィルという名前とグッドウィルをハンティング(Hunting)する、つまり探すという言葉が洒落た遊びになっている。「好意とか善良な意思を探し求める」という意味がこの映画のタイトルに重なりあっているのだ。、、、詳しくは是非お調べください。
このウィルは稀有な才能を持ち合わせているのだが、孤児であり、実は幼いころに受けた虐待のトラウマをもっている。そのせいで彼は自分の才能を生かせず、自暴自棄的な生き方をしているのだ。この青年の才能を見抜いたランボー教授は彼を何とか更生させようと心理学者たちに指導を仰ぐが、皆、天才にして膨大な知識をもつウィルに軽くあしらわれてしまう。ランボーは最後の手段として、学生時代の同級生で大学講師のショーン・マグワイア(ロビン・ウィリアムス)にカウンセリングを依頼する。実はこのショーンは最愛の妻を亡くしたことからやはり心に傷を負っていた。このショーンとウィルという共に心に傷を負う二人の間の葛藤がこの映画の中心になっている。
何故僕がこの映画を選んだのか?それはこの映画に散りばめられている、珠玉の名セリフがいつも心に刺ささり続けるからだ。生きるとは、教育とは、学びとは、、、、これらの事に関する沢山のヒントが満載なのです。その代表が「本当の知識、学びとは何か」に関して、以下のショーンのウィルに対する台詞だ!!このセリフはその後僕の学びに対する理解を、そして学び方自体を大きく変えるきっかけになった。ショーンは膨大な知識をひけらかすウィルに対してこう言う。
“So if I asked you about art, you’d probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo, you know a lot about him. Life’s work, political aspirations, him and the pope, sexual orientations, the whole works, right? But I’ll bet you can’t tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You’ve never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling; seen that. If I ask you about women, you’d probably give me a syllabus about your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can’t tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy.
(意訳します)「もし僕が君に(つまり天才ウィルに)芸術に関して問うたなら、恐らく君は芸術に関する本に書かれているあらゆる事細かな知識をすべて僕に答えて見せるだろう。ミケランジェロに関しても君は膨大な知識をもっているに違いない。彼の作品、政治的野心、彼と法王、そして彼の性的指向その他すべてを知り尽くしているんだろう!だがな、君は、例えばシスティーナ礼拝堂に立った時、どんなニオイを感じるのかを知りはしない。君はおそらく、そこに立ったことがないし、その美しい天井画を見上げた時の臨場感を知らないだろう。もし僕が君に女性に関して問うたなら、君はおそらく自分の好みのリストを事細かに描写してよこすだろう。君はもしかしたら何度かは女性を経験したかもしれない。だか、君は恐らく、朝目覚めたときに女性を傍に感じて心の底からの幸せを感じるという事がどんな事なのかを知りはしないはずだ」
今現在も、僕はこのセリフを胸に、自分が大学で教えている演劇史の舞台などを自分の足で歩き、そして自分の目で見、自分の肺で呼吸をして、肌で温度を感じて、全身でその臨場感を取り込む努力をしている。
因みに、この映画の後に僕はこのボストンに住みながら博士論文を書く機会に恵まれ、このMITのキャンパスを散歩しながら、論文の構想をねったりした思い出の場所ともなった。(でもMITの学生ではないです!!苦笑)
蛇足ながら、このマット・デーモンの在籍した、ハーバード大学は、ジョージ・ピアス・ベーカー教授という劇作の泰斗によるWorkshop 47 という劇作ゼミが1900年代初頭、全米で最初に起こった所でもある。これは教授がEnglish 47 というクラスで教え始めた劇作教室が進化したもので、ユージン・オニールなど、後のアメリカ演劇に多大な影響を及ぼす若者たちを沢山輩出している。日本では坪内逍遥先生の養子であった、坪内士行氏がこの教授に学んでいる。(その後、ベーカー教授は何とかハーバードに劇作の学位を授与するプログラムを作ろうと尽力するが、大学は頑なに拒否し、仕方なく教授はエール大学に赴き、現在、演劇学における全米最高峰のYale School of Drama を創設するに至る)

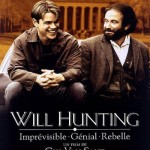

 さてさて元NHKエグゼクティブアナウンサーの村上信夫さんよりバトンを頂きました。第4日目は、これです。映画を語る時、自分の職業上絶対に避けられない映画。「天井桟敷の人々」です。
さてさて元NHKエグゼクティブアナウンサーの村上信夫さんよりバトンを頂きました。第4日目は、これです。映画を語る時、自分の職業上絶対に避けられない映画。「天井桟敷の人々」です。