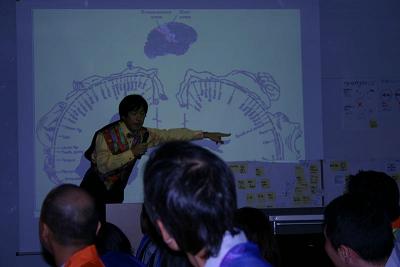オバマが第44代アメリカ大統領に当選した。優勢とは伝えられていてもブラッドリー効果、あるいはワイルダー効果といった根強い白人の人種偏見に基づく予想と結果の間の落差にアメリカ人の多くが不安とと期待に緊張の時間を過ごしたことだろう。しかし、アメリカ国民はもうブッシュ政権の新自由主義経済およびイラクの泥沼ににうんざりしていたのだ。そして今日オバマの大統領受諾演説を聴いた。聴いているうちに多くのアメリカ人と一緒にボロボロと涙している自分に気づいた。この最悪の時期にオバマのスピーチはなんと効果的に国民に夢と希望と自信を与えている事か!凄い。本当にすごすぎる!
高校生の頃にJFK(ケネディー大統領)の就任演説に触れ、それに恋してしまった自分は無我夢中になってその一言一言を当時のカセットテープを聞きながら全スピーチを暗唱した。そしてその内容に本当に心から惚れていたのだが、今日のオバマのスピーチはそれに勝るとも劣らない名演説だった。
リンカーンの掲げた夢を要所要所に掲げ、今日、各小学校、集会所に何時間も列をなして並んで投票したすべての人々の自由への功績をたたえ、富裕層、貧困層、すべての人種、ゲイ、ハンディキャップ、その他すべての人々に主人公として団結することを訴えた。また、アトランタで今日列に並び投票した106才の一アフリカ系アメリカ人の老女の話をした。奴隷制度のなごりの時代から始まり、彼女が今日まで106年間目にしてきたであろう歴史の一こま一コマを回顧しながら、女性であるがゆえに、そして肌の色のため故に発言権を奪われ、抑圧されながらも目撃したアメリカの自由への戦いを振り返るように語り続けた。奴隷制から始まり、30年代の大恐慌、第二次大戦を経て、アラバマ州モントゴメリーのバスボイコット事件に端を発した公民権運動、ベルリンの壁の崩壊。そして、その節々に”Yes, we can!”と鼓舞しながら、アメリカンドリームを実現してきたアメリカ国民をたたえた。そして106年目に、そしてこの最悪の状況のさ中、その老女はついに自ら投票ボードに手を差し伸べて自由に一票を投じたのだ。そうだ、私たちは出来る、イエス、ウィー、キャン!!この時点ですでに12万人以上の聴衆は声をそろえて”Yes, we can!”を合唱していた。目に涙をうかべながら・・・。そしてさらにオバマは国民に誘いかける、このような偉業を成し遂げたわれわれアメリカが今後彼女と同じく106年後に私たち子供たちに見せられる夢とは何か? 私たちの子供達がその時にどんな素晴らしいことを目撃できるのか?これが今日の私たちに投げかけられた問い(call)なのだと!そして国民は一様に叫んだ!イエス、ウィーキャン!!
民衆の目は潤みながら、しかも希望と夢に大きく深くうなづいていた。
こんな素晴らしい歴史の瞬間に、しかも自らの40代最後の日に立ち会えた自分を本当に幸せだと思った。そしてアメリカ国民と一緒に泣いた。やはりアメリカはまだまだ捨てたもんじゃないかもしれない。こんな希望に満ちあふれたかつてのアメリカが大好きだった。ケネディーのいたころのアメリカが戻ってきたような気がした。希望がある、夢がある。そうオバマは力説した。こんな素晴らしい政治家がいるアメリカがうらやましい。どん底の時こそ人々に必要なのは夢と希望と自信だ。間違ってもいい、それをみな一つになって乗り越えればいい。そんなことを教えてくれた。さてこれからこのアメリカがどう展開してゆくかが楽しみだ。できればこんな演説もぜひ暗唱してみたいな~!!
そしていつか日本でもこんなスピーチが聞きたい。
http://www.huffingtonpost.com/2008/11/04/obama-victory-speech_n_141194.html
-
ブログ最新エントリー
ブログカテゴリ
- イベント (7)
- つれづれなるままに (671)
- ひとりごと (259)
- ワークショップ (9)
- 中学校公演に寄せられた感想 (4)
- 公演 (28)
- 告知 (55)
- 学位 (4)
- 小学校公演に寄せられた感想 (3)
- 高校公演に寄せられた感想 (3)
以前の記事
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (4)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (3)
- 2024年9月 (1)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (8)
- 2023年10月 (2)
- 2023年7月 (10)
- 2023年6月 (3)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (4)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (1)
- 2021年11月 (3)
- 2021年7月 (3)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (4)
- 2020年1月 (2)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (5)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (3)
- 2018年12月 (7)
- 2018年11月 (9)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (7)
- 2018年8月 (11)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (5)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (3)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (10)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (5)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (8)
- 2013年6月 (6)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (6)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (5)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (10)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (7)
- 2012年7月 (9)
- 2012年6月 (10)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (8)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (10)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (7)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (6)
- 2011年7月 (11)
- 2011年6月 (10)
- 2011年5月 (6)
- 2011年4月 (8)
- 2011年3月 (14)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (9)
- 2010年12月 (11)
- 2010年11月 (13)
- 2010年10月 (9)
- 2010年9月 (10)
- 2010年8月 (6)
- 2010年7月 (9)
- 2010年6月 (7)
- 2010年5月 (8)
- 2010年4月 (13)
- 2010年3月 (14)
- 2010年2月 (10)
- 2010年1月 (5)
- 2009年12月 (12)
- 2009年11月 (10)
- 2009年10月 (14)
- 2009年9月 (10)
- 2009年8月 (10)
- 2009年7月 (11)
- 2009年6月 (9)
- 2009年5月 (12)
- 2009年4月 (6)
- 2009年3月 (10)
- 2009年2月 (16)
- 2009年1月 (11)
- 2008年12月 (10)
- 2008年11月 (8)
- 2008年10月 (12)
- 2008年9月 (4)
- 2008年8月 (13)
- 2008年7月 (18)
- 2008年6月 (9)
- 2008年5月 (11)
- 2008年4月 (7)
- 2008年3月 (13)
- 2008年2月 (6)
- 2008年1月 (12)
- 2007年12月 (9)
- 2007年11月 (5)
- 2007年10月 (5)
- 2007年9月 (8)
- 2007年8月 (2)
- 2007年7月 (14)
- 2007年6月 (6)
- 2007年5月 (5)
- 2007年4月 (13)
- 2007年3月 (1)
- 2007年1月 (1)
- 2006年12月 (2)
- 2006年9月 (1)
- 2006年7月 (3)
- 2006年5月 (1)
- 2006年4月 (1)
- 2006年3月 (1)
- 2005年12月 (1)