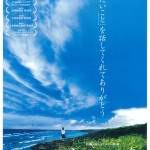 私の三日目の映画は柴田昌平監督のドキュメンタリー映画「ひめゆり」。沖縄戦における、ひめゆりの生存者の方々が生の声によりその体験を包み隠さず、正直に話して下さるドキュメンタリー。その内容はあまりにリアルで、、、そして聞いているうちに不思議なことにあまりのリアルさに、それらがシュールに思えてくるのだ。でも本当のリアルというのは、その現実を肌で知らない僕らにはシュールに聞こえるのは当然なのかもしれない。つい前日まで学校の校庭で仲間と戯れ、将来の夢に胸を膨らませていた14歳から19歳の少女達。その少女達が送られた世界は想像を絶するものだった。その凄まじい医療現場の描写が淡々となされる中、何もない病院の施設で脚や腕を片っ端から切断される重症患者を押さえつけ、そしてその切断されたばかりの腕や脚を捨てる為に持ち運ぶ悲惨な現実を描写しつつ、それらが現実には徐々に麻痺してくるのだという。これ以上の描写は避けるが、もう、これはこの世の生き地獄だ。よくもこれだけ辛い思いを話してくださった。嫌だったに違いない。思い出したくもなかったに違いない。この映画のポスターにも書かれているが、「忘れたいこと」を話してくれてありがとう。本当だ!!僕は心の中で手を合わせながら感謝していた。これは僕らが今まで全く知らなかった事。もしかしたら一生知りえなかった事だ。しかも、これらは僕らが知らなくてはならない事なのだ!なぜなら現実にこの国に起こったことであり、誰もそれを今まで生の声で伝えてくれていなかった。今日まで幸せな僕らが明日はこういう状況にならないという保証はない。本当に貴重な証言だ。そしてこの純粋な、あまりに純粋な若い少女たちを襲う最後の軍からの指令、、、各自自由解散。本当に知らなくちゃ!!これがこの国のやり方であり、今も全く変わっていないのだから!!実はこの映画、5年前から息子と二人で必ず6月23日、つまり沖縄戦終結の日に一緒に見に行っているのだ。息子も日にちが近づくと、そろそろだねと誘ってくる。それくらいこのひめゆりの人々の証言に心を揺さぶられ、ややもすると「平和」という事を当たり前のように思ってしまう麻痺感覚を正してくれるのだ、この映画は!!帰りの電車で毎回息子と長い長い話をする。珠玉の時間だ。
私の三日目の映画は柴田昌平監督のドキュメンタリー映画「ひめゆり」。沖縄戦における、ひめゆりの生存者の方々が生の声によりその体験を包み隠さず、正直に話して下さるドキュメンタリー。その内容はあまりにリアルで、、、そして聞いているうちに不思議なことにあまりのリアルさに、それらがシュールに思えてくるのだ。でも本当のリアルというのは、その現実を肌で知らない僕らにはシュールに聞こえるのは当然なのかもしれない。つい前日まで学校の校庭で仲間と戯れ、将来の夢に胸を膨らませていた14歳から19歳の少女達。その少女達が送られた世界は想像を絶するものだった。その凄まじい医療現場の描写が淡々となされる中、何もない病院の施設で脚や腕を片っ端から切断される重症患者を押さえつけ、そしてその切断されたばかりの腕や脚を捨てる為に持ち運ぶ悲惨な現実を描写しつつ、それらが現実には徐々に麻痺してくるのだという。これ以上の描写は避けるが、もう、これはこの世の生き地獄だ。よくもこれだけ辛い思いを話してくださった。嫌だったに違いない。思い出したくもなかったに違いない。この映画のポスターにも書かれているが、「忘れたいこと」を話してくれてありがとう。本当だ!!僕は心の中で手を合わせながら感謝していた。これは僕らが今まで全く知らなかった事。もしかしたら一生知りえなかった事だ。しかも、これらは僕らが知らなくてはならない事なのだ!なぜなら現実にこの国に起こったことであり、誰もそれを今まで生の声で伝えてくれていなかった。今日まで幸せな僕らが明日はこういう状況にならないという保証はない。本当に貴重な証言だ。そしてこの純粋な、あまりに純粋な若い少女たちを襲う最後の軍からの指令、、、各自自由解散。本当に知らなくちゃ!!これがこの国のやり方であり、今も全く変わっていないのだから!!実はこの映画、5年前から息子と二人で必ず6月23日、つまり沖縄戦終結の日に一緒に見に行っているのだ。息子も日にちが近づくと、そろそろだねと誘ってくる。それくらいこのひめゆりの人々の証言に心を揺さぶられ、ややもすると「平和」という事を当たり前のように思ってしまう麻痺感覚を正してくれるのだ、この映画は!!帰りの電車で毎回息子と長い長い話をする。珠玉の時間だ。実は事の始まりは6年前、息子が9歳だったころだった。3月10日の東京大空襲の日にNHKスペシャル特集ドラマ「東京が戦場になった日」をたまたま家族で見ていた。ドラマの内容はまさに東京大空襲で、あまり知られていなかった若者たちの悲劇を描いたものだった。帝都防災のために、「学徒消防隊員」(軍隊へ兵役猶予されていた理科系及び医系の学生)や「年少消防官」(18歳未満の少年)として駆り出され消防署に勤務させられた若者たちが、なんの訓練もなく当日空襲の中奮闘し、そして無残に犠牲者になって散って行くという物語。気が付くと、物凄い炎に包まれた東京を映す画面を見ながら、息子が目を真っ赤に腫らしながら大粒の涙を流し、テレビに向かって指をさし、大声でアメリカをののしっていた。9歳の息子がだ。「お前らアメリカ人をみんなぶっ殺してやる!バカヤロー!!」その声は震えていた。ちなみに息子はちょうど私が論文を書いていたころ、ボストンの病院で生まれたのでアメリカ国籍も持つ。だから余計に複雑だったのかもしれない。
これは大変だ!と事の重大さに気づいた僕は、その年を家族で戦争を考える年とすることに決めた。何故ならば僕の学問の専門は教育演劇学。実際に行動し、やってみて学ぶ方法論だ。もしこの状況をハンドルできないのなら、僕はこの学問を無駄に学んだ事になる。そう思った。三月の春休みにまずは鹿児島の知覧へ行き、特攻隊の展示などを見て回った。ちなみにそこを訪れた3月26日がなんと最初の特攻機がここから飛び立った日だと案内の方に教えられ、そして彼らが書き残していった手紙を読みながら家族で考えた。息子は混乱していた。そして5月の連休には沖縄を訪れ、豊見城市の旧海軍司令部壕から始まり、ひめゆりの塔、そして首里城の第32軍司令部壕跡などを回ってみた。沖縄戦を読みやすくした漫画、新里堅進さんの「沖縄決戦」を読み、比嘉 富子さんの「白旗の少女」を息子と一緒に読んだ。そして、この一連の学びの最終章として、夏休みにはアメリカに渡り、ウィスコンシン州の友人を訪ねた。ちょうど教育演劇の学会がミルウォーキーで開催されたのだ。アメリカの親友たちとしばらく過ごし、息子の誕生日(実に彼の誕生日は8月15日なのだ!!)を一緒に祝ってもらう。息子は混乱の連続だった。こんなに優しいアメリカ人と何故日本は戦わなくてはならなかったのか。なぜ優しい人間たちが悪魔のようになってしまうのか。、、、、などなど。その帰りにハワイへ寄り、パールハーバーを見学。戦艦アリゾナで真珠湾攻撃の悲惨さを学び、そしてその裏にある博物館にて終戦の際、日本が降伏文書に調印した船、戦艦ミズーリを訪れた。行く先々で息子と話しあい、戦争が何故起こるのか、そしてそれによって犠牲になるのは誰なのかを徹底的に話しあった。そしてミズーリの船上で、特攻に失敗した日本兵の若者が船長の判断により船員たちに懇ろに葬られた美談をききながら、実はこのミズーリ―号も沖縄戦においては沖から常に艦砲射撃をしており、例の「白旗の少女」などの周辺にその爆弾が被弾していたのだという事を考える。複雑だ。人間は置かれた立場により、まったく変わった方向性をもってしまうんだ。
息子は夏休みの終わりに、長い長い日記を書き終えた。そしてそこには大人も注目に値する考えが沢山ちりばめられていた。その翌年、沖縄戦の終結の日にたまたま上映会を知った僕が映画に行こうとすると、息子が「僕も行きたい」といってくれた。まだ10歳、、、果たして、、、と思ったが、でも彼はもうすでにたくさん学んでいたので大丈夫と思い、それ以後この映画は二人の自分たち自身に対する戒めの思いと、語り部の皆さんに対する感謝をするために訪れている。












