帰国後、ここのところ突然依頼された演芸場の代演やら、いよいよ締切間近の論文審査の評価などに追われて、またまたブログが滞ってしまった。論文審査の締切に追われ、悪夢をみるような思い(苦笑)
だが、そんな中、世界中に散らばっている教え子たちから嬉しいメールが続々と届いた一週間だった。アメリカ、中国、アフリカその他に留学中の大学生の教え子たち、そして韓国などに卒業後帰国した学生。自分で言うのもなんだか照れ臭いが、みな一様に授業が面白かった事、そして自分の授業により、演劇の楽しさ、舞台の面白さに目覚めた事を書いてくれていた。教えていて最高に嬉しいのがこういった反応を直にもらった時だ。でもこれって邪悪な梨園への道に若者を引きずりこんでいるのだろうか?(冗談・笑)
因みに近頃息子が見ているDVDのピノキオ(ディズニー版)をよくよく見てみると、なんと妖精によって半分人間にしてもらい、これからその「勇気と良心」を試されようとするピノキオに最初に訪れる試練がキツネ達に「劇場に誘われる事」なのであった!!おいおい、最初の試練が劇場かい?!(苦笑)つまり、子どもたちへの最初のメッセージが「よい子は劇場へ行きません」かな?(爆) ちなみにわが息子は現在言うことを聞かないと、プレジャーランド(ピノキオが再び学校をさぼって馬車に乗り込み連れて行かれる享楽のカーニバル遊園地で、やがてそこでは子供は皆堕落の果てにロバになってしまい、売られてゆく)に連れて行かれるというのが物凄く怖いらしい。(苦笑・別にむやみに脅かしているわけではなく、親の呼び声を無視してどこへ構わず走って行ってしまうと迷子になってしまうという比喩です。)
ところでイタリアを旅していて気付くのがこのピノキオのキャラクターの多彩さだ。そして、同時に私たちが如何に現代の商業主義によって歪められたイメージやストーリーを刷り込まれているかということ。ほとんど現代の日本人やアメリカ人がピノキオと聞いてイメージするものは、恐らくディズニーの例のアニメキャラクターだろうし、その筋書きだろう。しかし、原作のピノキオはディズニーとはイメージもストーリーも大きく異なるものなのだ。もともとこのピノキオとはイタリア、フィレンツェ出身ののカルロ・コッローディ(Carlo Collodi、1820-1890)という作家が1881年にローマの「子供新聞」の為に創造した童話で、出版は1883年で、実際にこの作品が人気を博すのは彼の死後であったという。詳しくは次回に!!
(写真はローマの街角で見かけたピノキオの人形と原作者のカルロ・コッローディ)

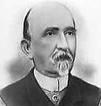
-
ブログ最新エントリー
ブログカテゴリ
- イベント (7)
- つれづれなるままに (671)
- ひとりごと (259)
- ワークショップ (9)
- 中学校公演に寄せられた感想 (4)
- 公演 (28)
- 告知 (55)
- 学位 (4)
- 小学校公演に寄せられた感想 (3)
- 高校公演に寄せられた感想 (3)
以前の記事
- 2025年7月 (3)
- 2025年6月 (2)
- 2025年5月 (4)
- 2025年1月 (3)
- 2024年12月 (3)
- 2024年9月 (1)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年1月 (3)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (8)
- 2023年10月 (2)
- 2023年7月 (10)
- 2023年6月 (3)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (6)
- 2022年11月 (4)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (1)
- 2021年11月 (3)
- 2021年7月 (3)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (2)
- 2021年2月 (3)
- 2021年1月 (5)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (1)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (5)
- 2020年5月 (4)
- 2020年1月 (2)
- 2019年11月 (5)
- 2019年10月 (5)
- 2019年8月 (3)
- 2019年7月 (5)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (1)
- 2019年3月 (1)
- 2019年2月 (3)
- 2018年12月 (7)
- 2018年11月 (9)
- 2018年10月 (8)
- 2018年9月 (7)
- 2018年8月 (11)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (4)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (1)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (5)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (4)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (3)
- 2017年4月 (3)
- 2017年3月 (2)
- 2016年12月 (1)
- 2016年11月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (10)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (4)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (3)
- 2015年8月 (1)
- 2015年7月 (5)
- 2015年6月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (3)
- 2014年12月 (5)
- 2014年11月 (5)
- 2014年10月 (4)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (3)
- 2014年6月 (6)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (5)
- 2014年3月 (5)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (2)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (4)
- 2013年10月 (6)
- 2013年9月 (4)
- 2013年8月 (4)
- 2013年7月 (8)
- 2013年6月 (6)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (6)
- 2013年3月 (5)
- 2013年2月 (5)
- 2013年1月 (6)
- 2012年12月 (7)
- 2012年11月 (10)
- 2012年10月 (9)
- 2012年9月 (10)
- 2012年8月 (7)
- 2012年7月 (9)
- 2012年6月 (10)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (8)
- 2012年3月 (8)
- 2012年2月 (6)
- 2012年1月 (10)
- 2011年12月 (7)
- 2011年11月 (9)
- 2011年10月 (7)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (6)
- 2011年7月 (11)
- 2011年6月 (10)
- 2011年5月 (6)
- 2011年4月 (8)
- 2011年3月 (14)
- 2011年2月 (11)
- 2011年1月 (9)
- 2010年12月 (11)
- 2010年11月 (13)
- 2010年10月 (9)
- 2010年9月 (10)
- 2010年8月 (6)
- 2010年7月 (9)
- 2010年6月 (7)
- 2010年5月 (8)
- 2010年4月 (13)
- 2010年3月 (14)
- 2010年2月 (10)
- 2010年1月 (5)
- 2009年12月 (12)
- 2009年11月 (10)
- 2009年10月 (14)
- 2009年9月 (10)
- 2009年8月 (10)
- 2009年7月 (11)
- 2009年6月 (9)
- 2009年5月 (12)
- 2009年4月 (6)
- 2009年3月 (10)
- 2009年2月 (16)
- 2009年1月 (11)
- 2008年12月 (10)
- 2008年11月 (8)
- 2008年10月 (12)
- 2008年9月 (4)
- 2008年8月 (13)
- 2008年7月 (18)
- 2008年6月 (9)
- 2008年5月 (11)
- 2008年4月 (7)
- 2008年3月 (13)
- 2008年2月 (6)
- 2008年1月 (12)
- 2007年12月 (9)
- 2007年11月 (5)
- 2007年10月 (5)
- 2007年9月 (8)
- 2007年8月 (2)
- 2007年7月 (14)
- 2007年6月 (6)
- 2007年5月 (5)
- 2007年4月 (13)
- 2007年3月 (1)
- 2007年1月 (1)
- 2006年12月 (2)
- 2006年9月 (1)
- 2006年7月 (3)
- 2006年5月 (1)
- 2006年4月 (1)
- 2006年3月 (1)
- 2005年12月 (1)


















